災害時の行動マニュアル
火災発生時の3大原則
1.初期消火
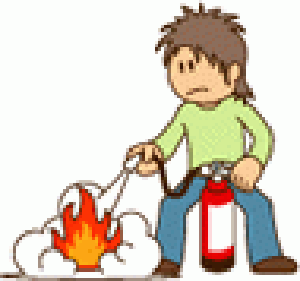
近くの消火器・屋内消火栓で初期消火に努める。あわせて、火災発生を大声で他者に伝える。炎が天井まで燃え移ったら限界である。避難すること。
2.119番通報
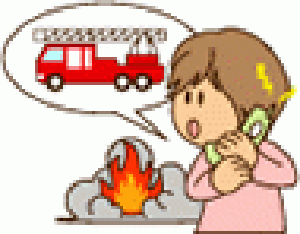
小さな火災でもすぐ119番通報する。慌てず正確に火災発生場所を告げる。
3.避難誘導

構内放送や大声による避難誘導をする。人命第一。
地震発生時の3大原則
1.身の安全確保
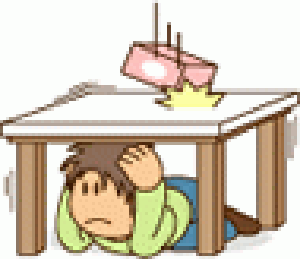
- 急いで机の下に隠れるなどして、落下物から自分の身の安全を確保する。
- 地震の揺れは長くても30秒程度(阪神・淡路大震災はわずか11秒であった)。慌てて外へ 飛び出るとかえって危険。直下型の大地震では身動きできない。
- 屋外にいたときは、建物のそばに近づかない。割れたガラスや看板などが落ちてくる場合もあるので危険。
2.火を消す

- 周りで火を使っていたらすぐ消す、止める。
- 燃え始めていたら初期消火活動(消火器・消火栓・119番通報)。
3.救援・救護
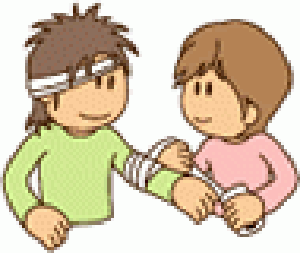
- 周囲にけが人はいないか、発見と救出。大声で安否を確認し合う。
- けがの手当て。大けがは119番通報で救急車を呼ぶ。
日頃の心がけが大切
一人ひとりが自分の身を自分で守れることが理想。身の安全を確保した上で、他人の救助・救援ができるよう心がける。
大規模災害発生時には
大学にいるとき
- 大規模災害発生時には、とにかく身の安全を確保する。
- 次に「周囲の火の始末・初期消火」を行う。
- 周りにけが人がいないか、大声で確認しあう(救護・救援活動)。
- 大学が情報収集に努め、その後の行動の指揮をとる。とにかく学校の指示に従う。帰宅するのが原則であるが、帰宅困難なときは、学校に留まる。
自宅または学外にいるとき
まず身の安全を確保する。通学途中・帰宅途中の場合は、本震が収まるのを待って、自宅に帰る。必ず家族と連絡を取り合い安全を確認する。「東海地震に関する情報」が出された場合
「注意情報」の段階で休講
東海地震が起こる可能性が高まったとしてテレビ、ラジオなどを通じて、気象庁から「注意情報」が出された段階で、直ちに授業を中止または休講とするため、以下のように行動すること。また、切迫度の高い「予知情報」「警戒宣言」が出された場合も、同様の措置をとる。- 在宅中は外出しない。
- 通学途中の場合は、速やかに自宅へ引き返す。
- 在校中は、大学および教職員の指示に従う。
「東海地震」に関する情報
東海地震発生の切迫度が高い順に(1)「予知情報」(2)「注意情報」(3)「観測情報」の三段階になっている。「予知情報」が出されると同時に内閣総理大臣から「警戒宣言」が発令される。「解除」後の授業再開
地震の恐れがなくなったとして「解除」された場合は、解除が発表された時間を基準に以下のとおり授業を再開する。- 午前5時までに解除された場合は、当日から平常どおり授業を行う。
- 午前5時以降に解除された場合は、翌日から授業を行う。
災害用伝言ダイヤルの使い方(携帯電話も同じ)
災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板である。◎「171(イナイ)」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音・再生を行う。
学生部 学生センター
〈2023年7月20日更新〉