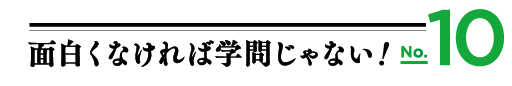
从犯罪中保护他人,保护自己
以“法”为出发点,
让我们思考“正确性”
以“法”为出发点,
让我们思考“正确性”


#亚大的研究
团城弘文教授
法学院法律系
2024.10.01
系列项目 "如果不有趣,那就不是学术!"介绍了亚细亚大学教师的研究和故事。第 10 版的特色是法学院法律系丹条博文教授是
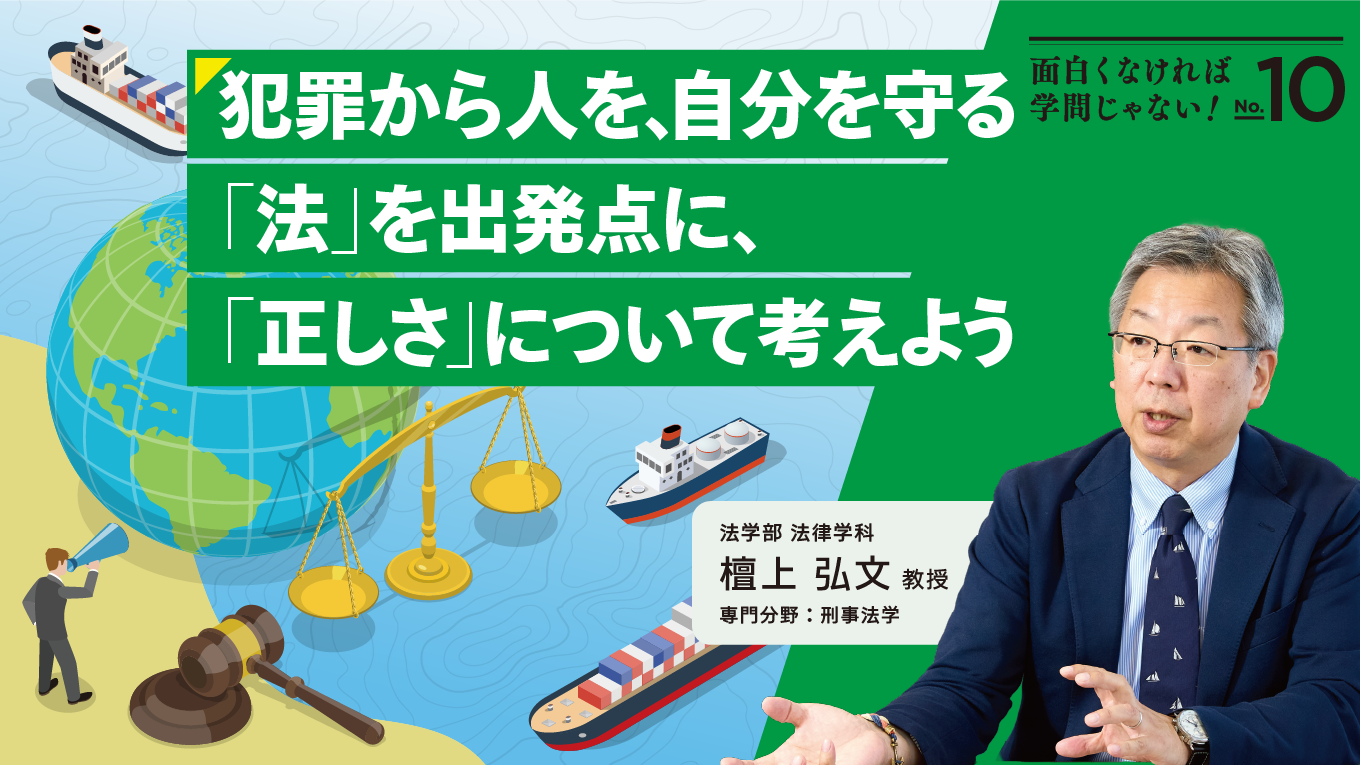
向往美国文化的大学生重新学习《刑法》的理由
回国后,我在大学主修文学和美国史,专注于这两个领域,毕业论文是19世纪作家亨利·戴维·梭罗。梭罗是《瓦尔登湖》的作者,该书描述了在自然环绕的湖畔自给自足的生活。梭罗也是一位著名的思想家和自然主义者。他对大规模生产和消费社会有着敏锐的洞察力,是一位先驱者,他的观察与当今的环境问题息息相关。他对文明社会的批判性眼光令我着迷。
当时,我曾梦想制作一档纪录片节目,来监督大众媒体的权力。然而,我很快意识到,自己缺乏对抗社会不公和公权力暴政的工具。这时,我想起了我在法学院通过跨系选课系统选修的“刑法”讲座。讲座内容非常有趣,我意识到,实现公正社会的“法律”将成为我从事社会工作的重要基础。因此,从文学院毕业后,我进入同一所大学的法学院学士,并研究生院继续攻读硕士和博士学位,主要研究“刑事诉讼法”。
海上这一国境地带的治安要依靠“法律”的理论武装来维护
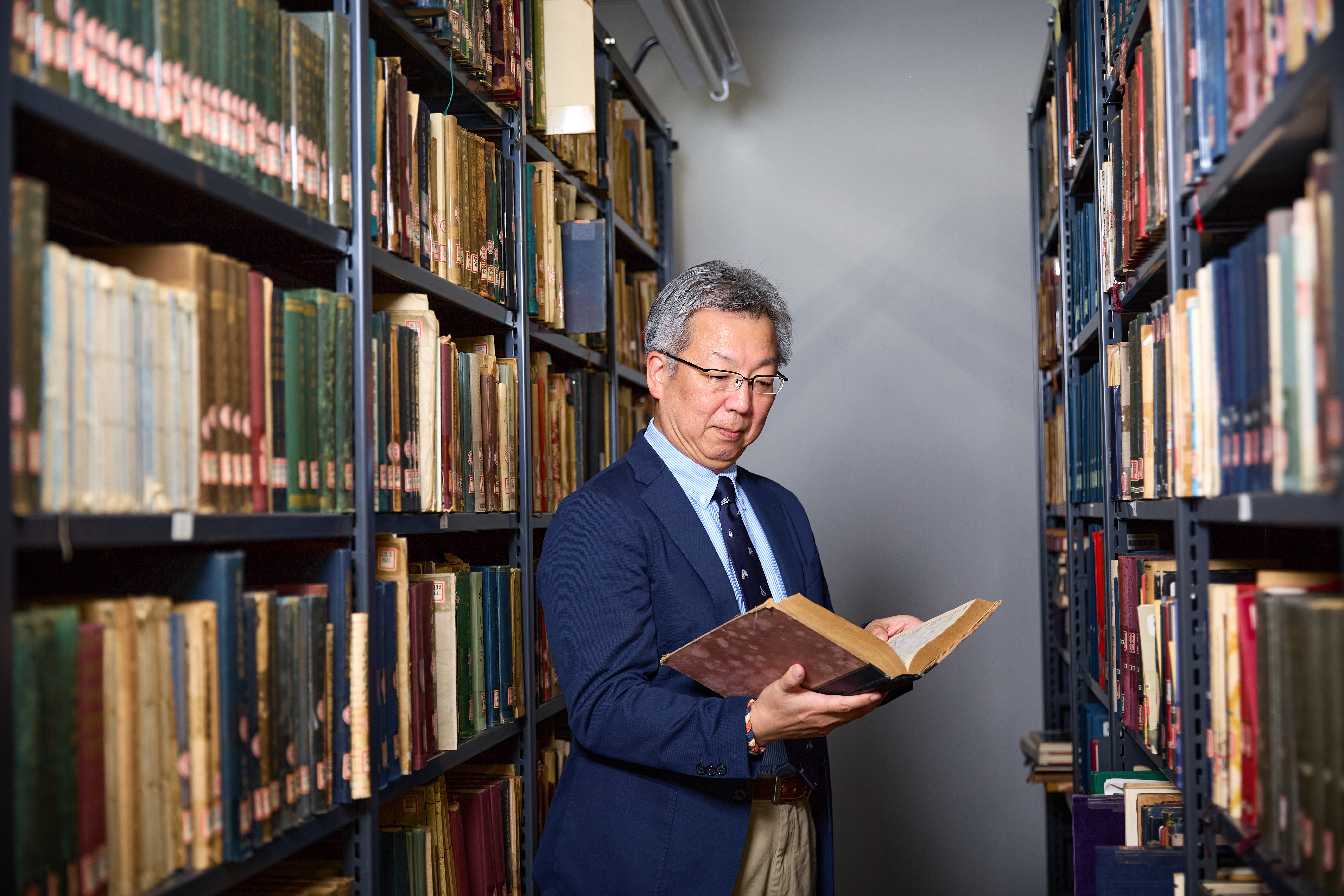
博士课程结束后,我听学长说有招聘,就去日本海上保安学院当了一名教员,讲授刑事诉讼法。海上保安官是国家公务员(日本海上保安厅,国土交通省的对外机构),负责“海上警察”的职务,而日本海上保安学院则培养高级警官。校友们教授航海、工程和通信等专业,但像我这样的普通大学研究人员有时也教授法律。
在日本海上保安学院,我为警官候选人讲座刑事诉讼法,并针对日本海上保安厅警官日常面临的海上犯罪以及边界和领海安全问题进行研究。
日本海上保安厅在我国领海的职责极其艰巨。日本领土面积不大,仅约38万平方公里(世界排名第61位),但其领海和专属经济区(EEZ,允许渔业和自然资源开采)的总面积约为其领土面积的12倍,位居世界第六。其海岸线长度更是高达惊人的3.5万公里。
对于四面环海的日本来说,海上是贸易和运输的重要通道,同时也是与邻国的边界。与陆地一样,边境地区也容易发生走私、偷渡、非法捕鱼等各种犯罪活动以及恐怖主义活动。近年来,中国渔船在冲绳县尖阁诸岛附近的日本专属经济区内非法作业,中国科考船也以海洋研究为名在水面上设置浮标。
日本海上保安厅的任务是维护边境和领海治安,打击这些政治上极其棘手的非法行为。为了执行这项任务,他们不仅需要武器,还需要掌握法律理论。我教授刑事诉讼法和其他课程,帮助他们更好地执行任务。
在日本海上保安学院,我为警官候选人讲座刑事诉讼法,并针对日本海上保安厅警官日常面临的海上犯罪以及边界和领海安全问题进行研究。
日本海上保安厅在我国领海的职责极其艰巨。日本领土面积不大,仅约38万平方公里(世界排名第61位),但其领海和专属经济区(EEZ,允许渔业和自然资源开采)的总面积约为其领土面积的12倍,位居世界第六。其海岸线长度更是高达惊人的3.5万公里。
对于四面环海的日本来说,海上是贸易和运输的重要通道,同时也是与邻国的边界。与陆地一样,边境地区也容易发生走私、偷渡、非法捕鱼等各种犯罪活动以及恐怖主义活动。近年来,中国渔船在冲绳县尖阁诸岛附近的日本专属经济区内非法作业,中国科考船也以海洋研究为名在水面上设置浮标。
日本海上保安厅的任务是维护边境和领海治安,打击这些政治上极其棘手的非法行为。为了执行这项任务,他们不仅需要武器,还需要掌握法律理论。我教授刑事诉讼法和其他课程,帮助他们更好地执行任务。
不仅在日本近海,在遥远的异国也进行执法的海上保安官
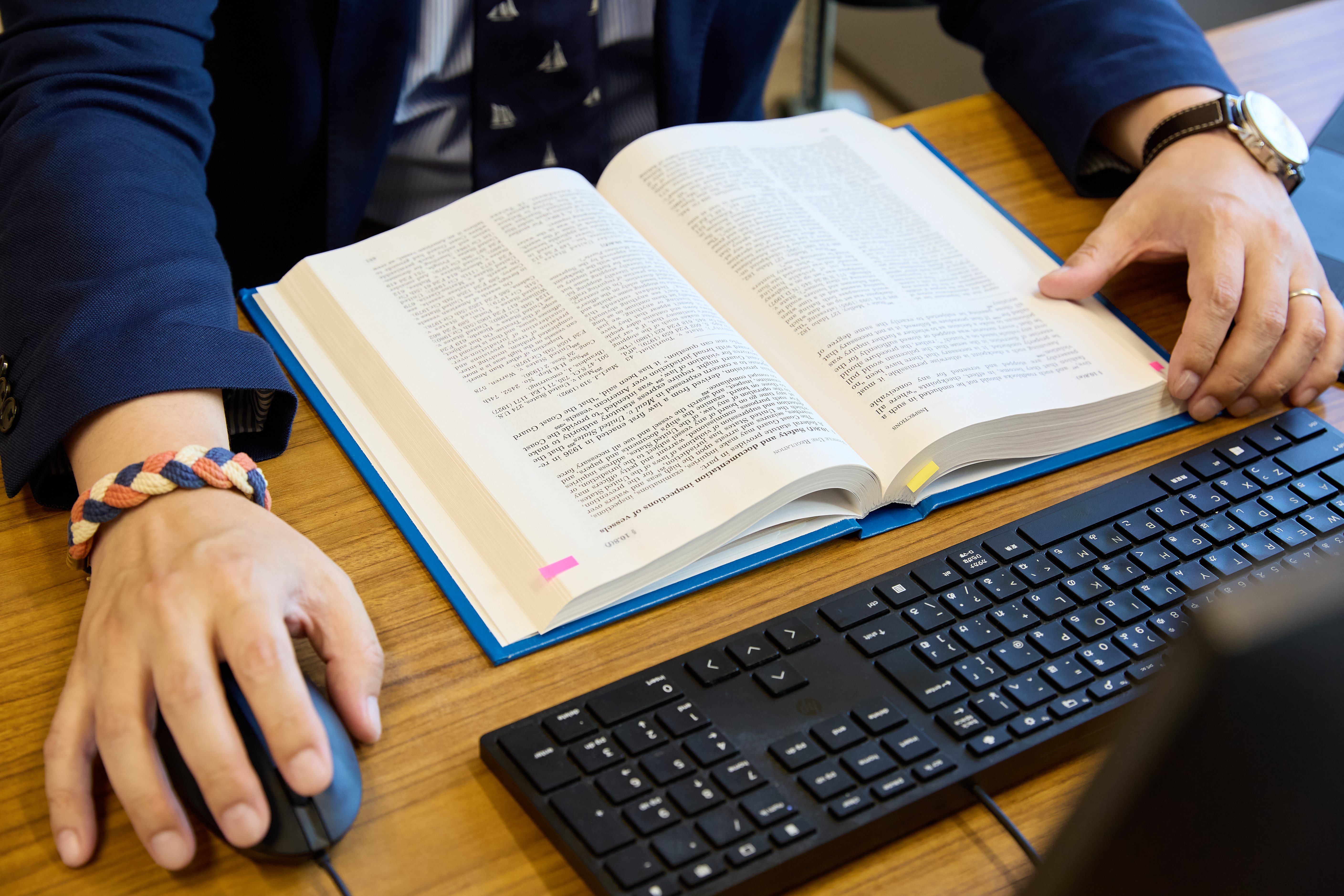
在日本海岸警卫队大学担任教员期间,我还访问了由日本国际协力机构 (JICA) 支持的菲律宾海岸警卫队 (海岸警卫队) 。菲我国海岸警卫队正在合作打击东南亚海域发生的海盗 (马六甲海峡经常发生) 。
1999年10月,巴拿马籍货船阿龙德拉·彩虹号从印度尼西亚港口出发前往日本,这是该海域海盗最有名的犯罪行为。海盗用救生用橡皮艇把船员扔到海里,连船体一起抢走了,是很凶恶的事件。幸运的是,乘坐橡皮艇漂流的船员在泰国普吉岛附近的渔船上安全获救,阿龙德拉·彩虹被印度海岸警卫队捕获。以这个事件为契机,海上保安厅和印度海岸警备队之间的关系构筑也在进行中。
与周边国家合作维护对日贸易非常重要的海域安全航行关系到我国的国家利益。因此,和周边国家进行关于海盗对策的会议和信息交换,还有海盗对策合作训练等。
夹在非洲大陆和阿拉伯半岛之间的亚丁湾、索马里海域发生的海盗问题长期以来成为国际社会的问题。各国向当地派遣了海盗对策部队,油轮等被袭击的日本也派遣了海上自卫队的海盗对策部队。您知道海上保安官同乘这个自卫队部队的护卫舰吗?因为自卫官没有司法警察权,所以海盗的逮捕等司法手续是由海上保安官进行的。这可能是一个意外未知的事实。
1999年10月,巴拿马籍货船阿龙德拉·彩虹号从印度尼西亚港口出发前往日本,这是该海域海盗最有名的犯罪行为。海盗用救生用橡皮艇把船员扔到海里,连船体一起抢走了,是很凶恶的事件。幸运的是,乘坐橡皮艇漂流的船员在泰国普吉岛附近的渔船上安全获救,阿龙德拉·彩虹被印度海岸警卫队捕获。以这个事件为契机,海上保安厅和印度海岸警备队之间的关系构筑也在进行中。
与周边国家合作维护对日贸易非常重要的海域安全航行关系到我国的国家利益。因此,和周边国家进行关于海盗对策的会议和信息交换,还有海盗对策合作训练等。
夹在非洲大陆和阿拉伯半岛之间的亚丁湾、索马里海域发生的海盗问题长期以来成为国际社会的问题。各国向当地派遣了海盗对策部队,油轮等被袭击的日本也派遣了海上自卫队的海盗对策部队。您知道海上保安官同乘这个自卫队部队的护卫舰吗?因为自卫官没有司法警察权,所以海盗的逮捕等司法手续是由海上保安官进行的。这可能是一个意外未知的事实。
在技术不断发展的时代,判断“正确性”的能力变得越来越重要

在日本海上保安学院担任教员期间,我深刻体会到在涉及其他国家国民的边境地区进行海上安全保卫的严酷性和令人沮丧的本质。例如,即使违法行为明明就在眼前发生,却因为加上了“国际问题”和“政治判断”的视角,而做出与“法理”结论不同的判断,有时会让我感到痛苦。
日本海上保安厅的队员们,每天在艰苦的环境中奋战,心中有时也怀着这样的苦涩。他们始终坚守着我国所制定的法律的正义……我希望未来将引领日本的年轻一代能够意识到这一现实。同时,我希望他们能够再次深刻思考:在一个法治国家,犯罪必须按照法律规定的程序和程序进行审判。
我希望大学生能够独立研究、思考什么是正义,并自信地做出判断。此外,无论论点多么正确,如果在执法过程中不遵循正确的“程序”,这种“正确性”就不会被认可。在我的“刑事诉讼法”课程中,我通过法律知识,让学生认识到不仅在法庭上,而且在社会生活中遵循正确程序的重要性,并希望他们能够认真讲座冲突双方的意见,并具备做出公正判断的意识。
未来,人工智能(AI)等尖端技术将应用于刑事调查。或许,AI 将在法庭上做出判决。然而,现行法律尚未完全兼容当今常见的技术,例如使用 GPS 进行调查。犯罪分子有可能利用最新技术与法律之间的“缝隙”逃脱法律制裁。另一方面,正是人类的智慧和在法庭上力求“做正确的事”的心灵,才能将受害者和弱势群体从这些“缝隙”中拯救出来。
深入思考“什么是对的”才是人类的智慧,这难道不正是大学四年真正应该做到的吗?这不仅是法学院学生,也是所有以大学为目标的学生最想传达的信息。
日本海上保安厅的队员们,每天在艰苦的环境中奋战,心中有时也怀着这样的苦涩。他们始终坚守着我国所制定的法律的正义……我希望未来将引领日本的年轻一代能够意识到这一现实。同时,我希望他们能够再次深刻思考:在一个法治国家,犯罪必须按照法律规定的程序和程序进行审判。
我希望大学生能够独立研究、思考什么是正义,并自信地做出判断。此外,无论论点多么正确,如果在执法过程中不遵循正确的“程序”,这种“正确性”就不会被认可。在我的“刑事诉讼法”课程中,我通过法律知识,让学生认识到不仅在法庭上,而且在社会生活中遵循正确程序的重要性,并希望他们能够认真讲座冲突双方的意见,并具备做出公正判断的意识。
未来,人工智能(AI)等尖端技术将应用于刑事调查。或许,AI 将在法庭上做出判决。然而,现行法律尚未完全兼容当今常见的技术,例如使用 GPS 进行调查。犯罪分子有可能利用最新技术与法律之间的“缝隙”逃脱法律制裁。另一方面,正是人类的智慧和在法庭上力求“做正确的事”的心灵,才能将受害者和弱势群体从这些“缝隙”中拯救出来。
深入思考“什么是对的”才是人类的智慧,这难道不正是大学四年真正应该做到的吗?这不仅是法学院学生,也是所有以大学为目标的学生最想传达的信息。