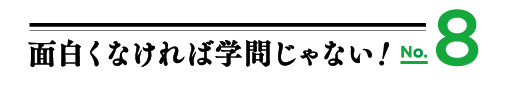
谁都是国际社会的一员,
“国际和平”的走向
不是遥远国家的问题!
“国际和平”的走向
不是遥远国家的问题!


#亚大的研究
向井若菜副教授
国际关系学院国际关系系
2024.08.01
在“如果不有趣,就不是学术!”系列中,我们介绍了亚细亚大学教职员工的研究内容和轶事。第八位嘉宾是国际关系学院国际关系系副教授。

我想知道这个世界是如何运转的
渐渐地,我开始对世界如何运转以及它如何运作产生了兴趣,这始于高中的“政治与经济”课程。我对国际政治的兴趣与日俱增,最终考入东京外国语大学外国语系英语专业,因为这是一所可以学习国际政治并提高英语水平的大学。大三和大四的时候,我参加了期盼已久的国际关系研讨会,拓宽了我对国际社会的了解。在此期间,我偶然在报纸上读到一篇专题报道,了解到“无核武器区”倡议。我想进一步了解“核武器”的军事和政治力量如何动摇国际政治,以及国际社会为此所做出的和平努力,于是就此撰写了毕业论文。在此期间,我从其他大学的图书馆借阅了大学里没有的资料,甚至还去大阪大学与核裁军研究领域的顶尖专家进行了交流。
大学毕业后,我曾想过在联合国或其他组织工作,为实现“无核武器世界”做出贡献。为此,我至少需要在研究生院获得硕士学位。因此,大学毕业后,我进入东京研究生院。在国际政治权威藤原喜一教授的指导下,我研究了围绕核武器的国际政治,尤其关注核裁军方面,并最终(虽然花费了很长时间)获得了博士学位。
国际社会面向“核裁军”的措施是什么?

我在研究生院接受了研究员培训,之后在一家智库担任研究员,之后来到亚细亚大学国际关系学院任教。
自从成为大学教授以来,我意识到自己热爱教学。与此同时,我也深知教学的艰辛。包括我在内的大学教授都是以研究为职业的人,很多情况下,他们并不像高中教师那样持有教师资格证——这是专业教学的证明。相反,我们每个人都是各自领域的“专业人士(专家)”。我每天都在思考如何以通俗易懂的方式讲授我一直以来感兴趣并研究的国际政治和核裁军问题,以便学生们能够将其视为“他们自己的问题”。
在本科课程“国际政治导论”和“国际安全理论”中,我们讲解了研究国际政治的意义及其主要议题。“全球治理”是一门面向高年级学生的课程,全英语授课。三、四年级学生的研讨课主题是“从安全视角看待世界”,我经常与学生讨论我的专业领域,例如核裁军和军备控制。我不仅教授学生知识,也经常从讨论中学习。
我们都知道核武器对人类构成巨大威胁。尤其是我们这些生活在战争时期遭受原子弹轰炸的国家的人,从小就深知核武器造成的破坏有多么巨大。
然而,即使在原子弹爆炸80年后的今天,世界仍然面临核武器的威胁。当然,国际社会并没有袖手旁观。1970年生效的《不扩散核武器条约》(NPT)承认了国际社会已经存在核武器的现实,并以此为基础制定了三大支柱:“核裁军”(主要在《不扩散核武器条约》允许拥有核武器的五个国家(美国、俄罗斯、英国、法国和中国)之间削减核武器的努力)、“核不扩散”(防止核武器及相关设备和技术在世界范围内进一步扩散的努力)以及“和平利用核能”(保障缔约国拥有将核能用于和平目的的不可剥夺的权利)。目前已有191个国家加入了该条约。然而,除了这五个国家之外,还有巴基斯坦、印度、朝鲜和以色列等九个国家拥有核武器。条约的存在并非能够解决问题的简单框架。为了应对这种情况,国际社会仍在继续做出各种努力,以减少核武器的数量。
自从成为大学教授以来,我意识到自己热爱教学。与此同时,我也深知教学的艰辛。包括我在内的大学教授都是以研究为职业的人,很多情况下,他们并不像高中教师那样持有教师资格证——这是专业教学的证明。相反,我们每个人都是各自领域的“专业人士(专家)”。我每天都在思考如何以通俗易懂的方式讲授我一直以来感兴趣并研究的国际政治和核裁军问题,以便学生们能够将其视为“他们自己的问题”。
在本科课程“国际政治导论”和“国际安全理论”中,我们讲解了研究国际政治的意义及其主要议题。“全球治理”是一门面向高年级学生的课程,全英语授课。三、四年级学生的研讨课主题是“从安全视角看待世界”,我经常与学生讨论我的专业领域,例如核裁军和军备控制。我不仅教授学生知识,也经常从讨论中学习。
我们都知道核武器对人类构成巨大威胁。尤其是我们这些生活在战争时期遭受原子弹轰炸的国家的人,从小就深知核武器造成的破坏有多么巨大。
然而,即使在原子弹爆炸80年后的今天,世界仍然面临核武器的威胁。当然,国际社会并没有袖手旁观。1970年生效的《不扩散核武器条约》(NPT)承认了国际社会已经存在核武器的现实,并以此为基础制定了三大支柱:“核裁军”(主要在《不扩散核武器条约》允许拥有核武器的五个国家(美国、俄罗斯、英国、法国和中国)之间削减核武器的努力)、“核不扩散”(防止核武器及相关设备和技术在世界范围内进一步扩散的努力)以及“和平利用核能”(保障缔约国拥有将核能用于和平目的的不可剥夺的权利)。目前已有191个国家加入了该条约。然而,除了这五个国家之外,还有巴基斯坦、印度、朝鲜和以色列等九个国家拥有核武器。条约的存在并非能够解决问题的简单框架。为了应对这种情况,国际社会仍在继续做出各种努力,以减少核武器的数量。
通往漫长而险峻的“无核世界”之路
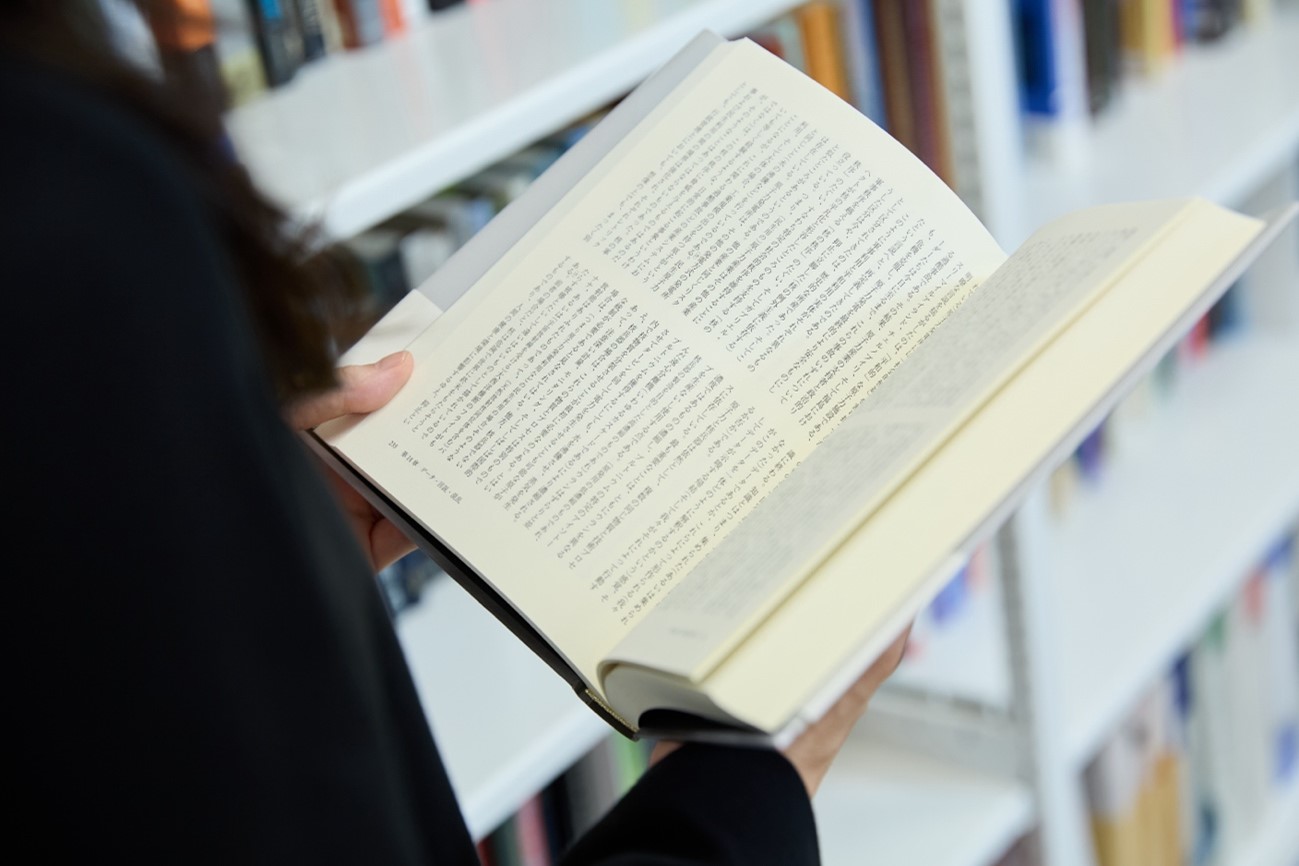
2009年,时任美国总统奥巴马在捷克首都布拉格宣布了美国率先推行“无核武器世界”的决心,并提出了实现这一目标的具体目标。这篇“布拉格演讲”中,奥巴马总统提到了美国作为唯一使用过核武器的核大国所负有的道义责任,触动了世界人民的心。同年,奥巴马总统荣获诺贝尔和平奖。
2017年,第一部全面依法禁止核武器的国际条约《禁止核武器条约》获得通过(将于2021年生效)。
2023年,在原子弹爆炸地广岛举行的七国集团峰会上,发表了首份以核裁军为主题的七国集团领导人共同文件——《七国集团领导人广岛核裁军愿景》。我认为,七国集团领导人有机会参观广岛和平纪念资料馆,直接聆听原子弹爆炸幸存者的心声,意义非凡。来自广岛的岸田文雄首相也表达了深切的慰问。
然而,现实是,通往“无核武器世界”的道路依然漫长而艰难。遭受俄罗斯入侵的乌克兰总统泽连斯基也出席了在广岛举行的七国集团峰会。针对乌克兰局势,俄罗斯总统普京近期下令实施射程可达欧洲的战术核武器实践。此外,在局势高度紧张的巴勒斯坦加沙地带,以色列内阁部长表示,“投掷原子弹是一种选择”,因为该国正在加强对伊斯兰组织哈马斯的攻势。
对日本而言,拥有核武器的中国入侵台湾的可能性、朝鲜进行核实验的可能性,甚至朝鲜在日本海进行导弹实验的可能性,都是国家安全的重要议题。实现“无核武器世界”的唯一途径,是生活在地球上的我们每个人都认识到我们是一个命运共同体,为了一百年后的子孙后代,一步步朝着和平的方向努力。为了实现这一目标,国际关系系提供的“教育”至关重要。该教育通过学习政治制度、国际法、外交、发展合作、经济、商业以及国际政治等各个领域,培养具有和平意识的“人”。
2017年,第一部全面依法禁止核武器的国际条约《禁止核武器条约》获得通过(将于2021年生效)。
2023年,在原子弹爆炸地广岛举行的七国集团峰会上,发表了首份以核裁军为主题的七国集团领导人共同文件——《七国集团领导人广岛核裁军愿景》。我认为,七国集团领导人有机会参观广岛和平纪念资料馆,直接聆听原子弹爆炸幸存者的心声,意义非凡。来自广岛的岸田文雄首相也表达了深切的慰问。
然而,现实是,通往“无核武器世界”的道路依然漫长而艰难。遭受俄罗斯入侵的乌克兰总统泽连斯基也出席了在广岛举行的七国集团峰会。针对乌克兰局势,俄罗斯总统普京近期下令实施射程可达欧洲的战术核武器实践。此外,在局势高度紧张的巴勒斯坦加沙地带,以色列内阁部长表示,“投掷原子弹是一种选择”,因为该国正在加强对伊斯兰组织哈马斯的攻势。
对日本而言,拥有核武器的中国入侵台湾的可能性、朝鲜进行核实验的可能性,甚至朝鲜在日本海进行导弹实验的可能性,都是国家安全的重要议题。实现“无核武器世界”的唯一途径,是生活在地球上的我们每个人都认识到我们是一个命运共同体,为了一百年后的子孙后代,一步步朝着和平的方向努力。为了实现这一目标,国际关系系提供的“教育”至关重要。该教育通过学习政治制度、国际法、外交、发展合作、经济、商业以及国际政治等各个领域,培养具有和平意识的“人”。
建设和平的世界需要每个人的“思考能力”

当我对我上课的学生进行调查时,许多学生表示,由于乌克兰、加沙地带以及朝鲜导弹实验等事件,他们对国际政治和核武器产生了浓厚的兴趣。通过新闻了解乌克兰和加沙地带局势的学生一定意识到,强权冲突并不能创造一个和平的世界。“为什么国家之间会发生冲突?”“为什么我们不能消除可能毁灭人类的核武器?”“为什么我们这一代的年轻人遭受如此多的苦难?”我希望尽可能多地培养学生走向世界,让他们意识到这些问题,将世界正在发生的事情视为自己的问题,并拥有独立思考的能力。
这是因为,包括核武器问题在内的整个国际政治进程,与国内社会状况、经济、金融乃至能源问题息息相关,并将极大地影响学生们的未来。18岁以上的大学生已经被赋予了创造和平世界的“接力棒”。将他们联系在一起的行动之一就是“投票”。尽管最近人们担心投票率下降,但在我的研讨会上,我们深入探讨了投票的意义,每个人都会投票给他们所期望的、能够根据自己的想法创造更美好社会的候选人。我希望尽可能多的人能够学会运用课堂和研讨会上学到的知识,独立思考和行动。
我之前说过“喜欢教学”,更确切地说,是“喜欢看着学生们在我眼前成长”。能够成为一名大学教授,我感到无比荣幸,因为我能够发现学生们身上蕴藏的天赋,帮助他们发展,并帮助他们做好步入社会的准备。我会继续磨练我的专业技能,不辜负他们的期望,为实现“无核武器世界”贡献哪怕是微薄的力量。每年看着许多学生成长,离开家,走向社会,我的这种感受都会不断更新。
这是因为,包括核武器问题在内的整个国际政治进程,与国内社会状况、经济、金融乃至能源问题息息相关,并将极大地影响学生们的未来。18岁以上的大学生已经被赋予了创造和平世界的“接力棒”。将他们联系在一起的行动之一就是“投票”。尽管最近人们担心投票率下降,但在我的研讨会上,我们深入探讨了投票的意义,每个人都会投票给他们所期望的、能够根据自己的想法创造更美好社会的候选人。我希望尽可能多的人能够学会运用课堂和研讨会上学到的知识,独立思考和行动。
我之前说过“喜欢教学”,更确切地说,是“喜欢看着学生们在我眼前成长”。能够成为一名大学教授,我感到无比荣幸,因为我能够发现学生们身上蕴藏的天赋,帮助他们发展,并帮助他们做好步入社会的准备。我会继续磨练我的专业技能,不辜负他们的期望,为实现“无核武器世界”贡献哪怕是微薄的力量。每年看着许多学生成长,离开家,走向社会,我的这种感受都会不断更新。