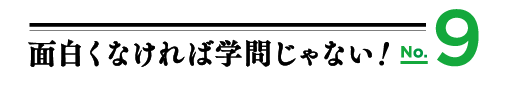
「GDP」では測れない
新たな経済政策の目標
「 Well-being 」って何?
新たな経済政策の目標
「 Well-being 」って何?


#亜大の研究
茨木 秀行 教授
経済学部 経済学科
2024.09.01
シリーズ企画「面白くなければ学問じゃない!」では、亜細亜大学の教員陣の研究内容やエピソードを紹介します。第9回の特集は、経済学部 経済学科 茨木 秀行 教授です。
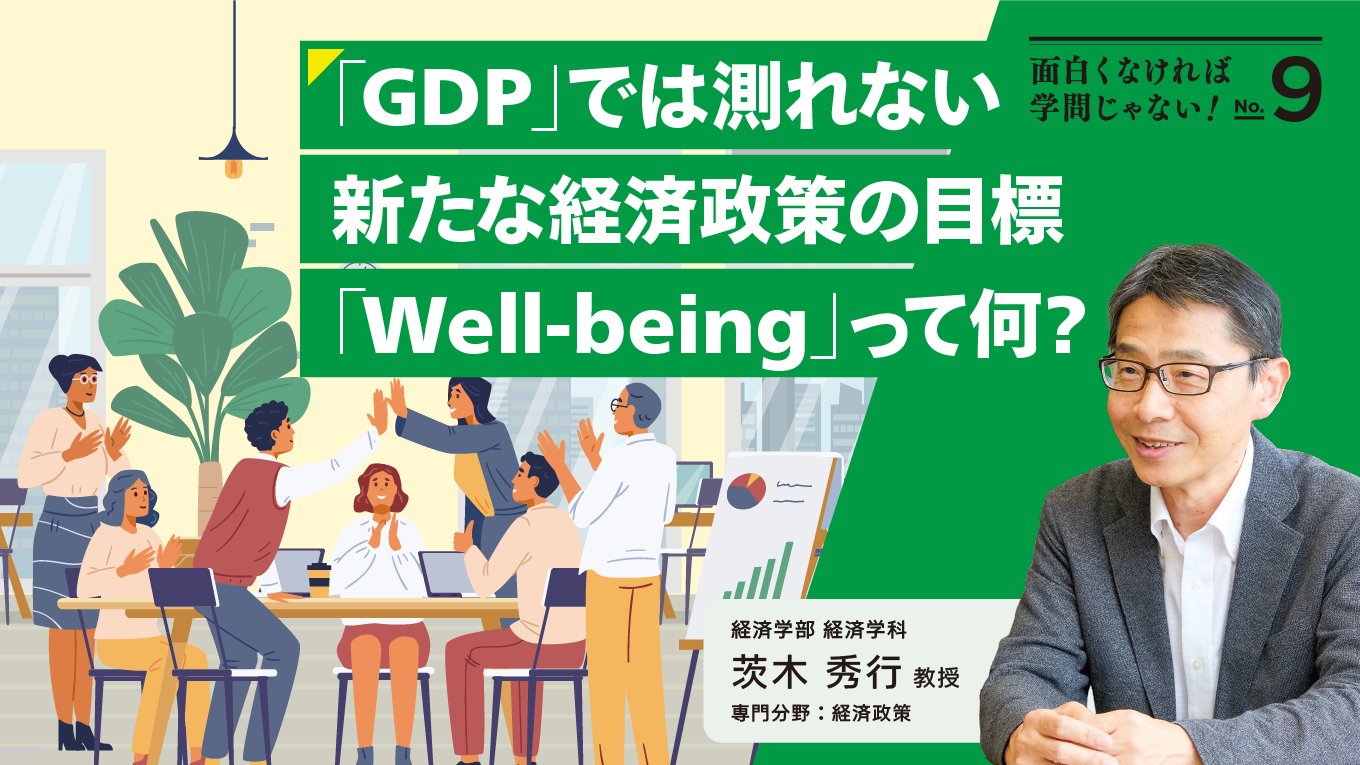
⼤学で学んだ経済学で豊かな社会をつくる仕事がしたい
経済官僚時代には英国の大学院に留学し修士号を取得し、その後、2度に渡ってフランス・パリに本部を置くOECD(経済協力開発機構)にも赴任しました。
2009年からの2度目のOECD赴任では、日本政府代表部参事官として政府の意向をOECDの議論に反映させる重要な任務を果たすこととなりました。私は主にOECDにおける経済政策と統計業務を担当し、その時にOECD統計局が取り組んでいた「 Well-being 」、すなわち幸福度・生活満足度を計る指標づくりの取り組みと出会ったのです。
「Well-being」との出会いはパリのOECD本部

ちょうど同じ時期にあたる2008年、世界経済に激震が走りました。米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻をきっかけに世界的な金融危機と大不況に発展した「リーマンショック」です。この出来事はそれまでの市場経済メカニズムへの信頼とグローバル化を牽引してきた「新自由主義」に基づく経済政策の限界をも示す出来事でした。
そうした事態を受けて、それまでGDP成長率を高めることに重点を置いてきた経済政策のあり方を見直す機運が高まり、新たな政策目標として、「 Well-being 」=幸福度の視点が、世界的な注目を集めるようになりました。OECDでもスティグリッツ委員会の報告書をベースに2011年に「より良い暮らしの指標(Better Life Index: BLI)」を開発しました。
ただし最初からすべてのOECD加盟国が「 Well-being 」の取り組みに賛同していたわけではありません。「幸福度」というきわめて主観的で、個別的な価値観を客観的であるべき経済指標に導入することへの抵抗感があったからです。
しかし、従来の「経済成長至上主義」がもはや通用しなくなっていることは明らかでした。そこで日本政府は初期の段階からOECDの「 Well-being 」の取り組みを積極的に支持してきました。当時の政権も幸福度の向上を重要な政策目標とし、そのための指標づくりに取り組むことを掲げました。OECD日本政府代表部にいた私は、OECD統計局の人々と緊密に連絡を重ねながら、日本政府から研究資金の提供を行うなどBLIの立ち上げに深く関わることになりました。
「BLI」以降、他の国際機関でも「Well-being」の取り組みが活発になり、国連では2012年より「世界幸福度報告」を毎年発表しているほか、GDPに代わる経済指標「Beyond GDP」の検討も行われています。そして現在までの間にOECD加盟国のうち日本を含む35カ国で「 Well-being 」計測の取り組みが進んできました。こうした世界的な「 Well-being 」に対する注目度の高まりは、OECDで最初期から深くこの課題と関わってきた私にはとても感慨深いものがあります。
⼈⼝減少社会では「Well-being」を⾼める働き⽅改⾰が鍵を握る
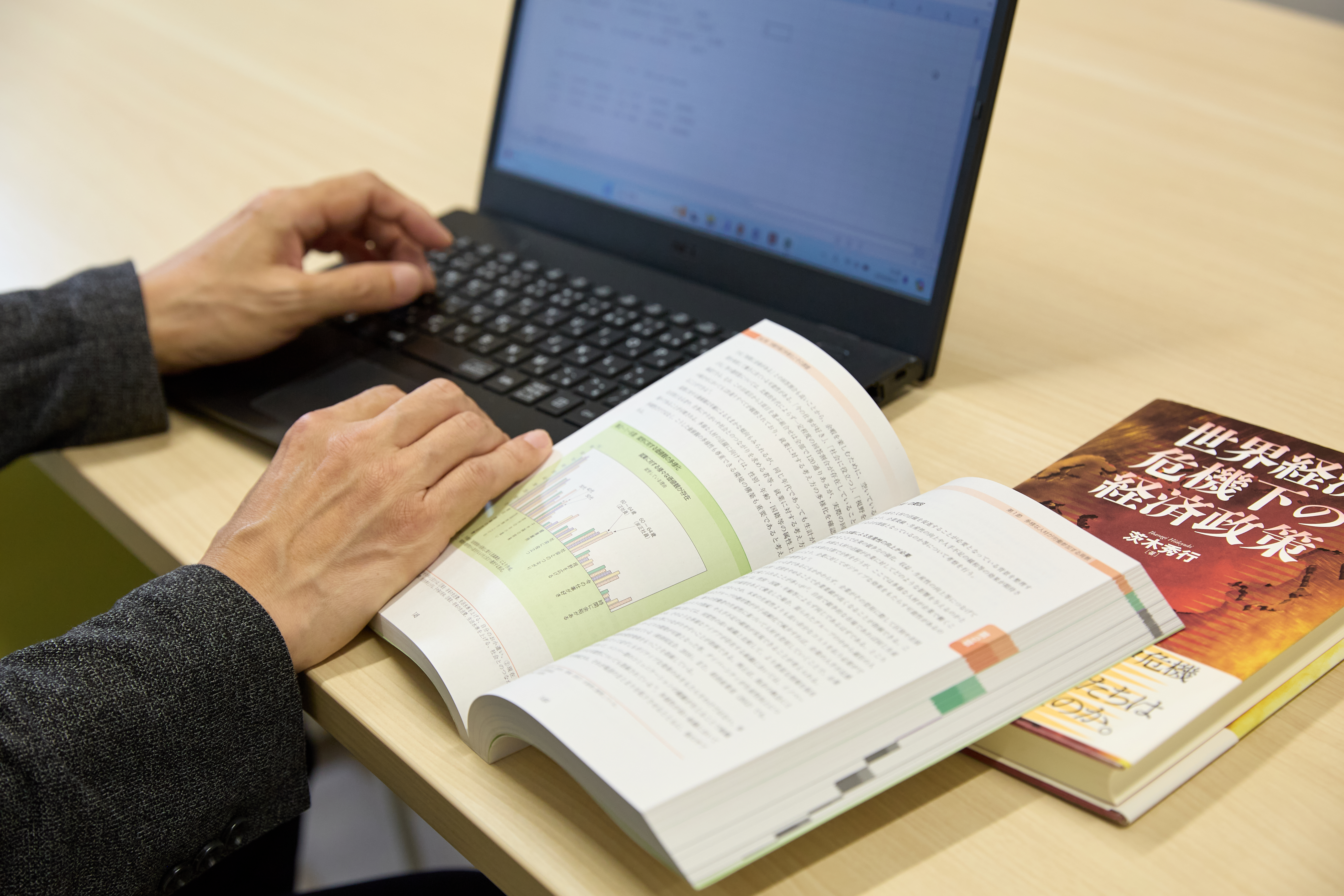
「Well-being」計測に関しては、客観的な指標によるものと個人へのアンケート調査を通じた主観的な満足度・幸福度を計測する2つの手法があります。OECDの「BLI」は前者で、日本政府(内閣府)が2019年より毎年1回実施している「満足度・生活の質に関する調査」は主に後者に相当します。
2023年度「満足度・生活の質に関する調査」では、人手不足の中で従業員の定着を図るための働き方改革に取り組む企業が増えていることを踏まえ、「やりがい」など自分の仕事をどう感じているかについても調査しています。それによると、同じ年収であれば「仕事のやりがい」を感じている人の方が満足度が高く、また「仕事のやりがいを感じている年収300万円未満」の人の方が「やりがいを感じていない年収700万円以上」の人より満足度が高いことも示されました。このように、「やりがい」を高めるWell-beingの視点は企業の人事管理にも役立つことが示されています。
また「BLI」の調査結果を見ると日本人は「仕事と生活のバランス」「社会とのつながり」の数値が世界的に見ても下位になっています。これは長時間労働をしている人の割合がOECD加盟国の平均より多いことによると考えられます。知人や地域の人との交流を通じ、良好な人間関係を築くことが健康と幸福感に大きな影響を与えることが多くの研究によって示されていますが、仕事中心の生活では社会とのつながりは希薄になりがちです。近年の「働き方改革」やコロナ禍を機にリモートワークなど柔軟な働き方が定着してきたため、「生活と仕事のバランス」は改善の傾向にはあるとはいえ、今後も政府・民間企業が力を合わせて取り組むことが必要です。人口減少社会において、希少な労働力を活かすためには、雇用や人事の面で「Well-being」の視点はますます重要となるでしょう。
最初に述べたとおり、私が就職した頃は、日本はバブル経済の最中にあり、私たちの世代は高級車やブランドの服など、ひたすら物質的な豊かさを追い求めていました。正直に申し上げますと、今でも自分の中にその名残である「物欲」が残っていることをしばしば感じています。
ところが、今の若者世代は必ずしも物の値段にこだわることなく、自分流に生活をエンジョイしているように見えます。多様な情報が簡単に入手できるネット社会になったことも、物質的な豊かさだけではない価値観やネットを通じた他人との関係性を重視する新しいライフスタイルを生み出している一因でしょう。就職活動に際しても、現代の大学生は、私たちの時代のように必ずしも大企業志向や出世欲ではなく、ワークライフバランスを重視し、自分の専門性や「やりたいこと」を第一に考えて志望企業を選ぶ傾向が見られます。身近な学生たちを見ていても、大学生の頃の自分よりずっと「Well-being」の本質を理解しているのではないかと思え、こうした若い世代に広がる価値観の転換が、やがて企業や政府を動かす原動力になるのではないかと感じています。
2023年度「満足度・生活の質に関する調査」では、人手不足の中で従業員の定着を図るための働き方改革に取り組む企業が増えていることを踏まえ、「やりがい」など自分の仕事をどう感じているかについても調査しています。それによると、同じ年収であれば「仕事のやりがい」を感じている人の方が満足度が高く、また「仕事のやりがいを感じている年収300万円未満」の人の方が「やりがいを感じていない年収700万円以上」の人より満足度が高いことも示されました。このように、「やりがい」を高めるWell-beingの視点は企業の人事管理にも役立つことが示されています。
また「BLI」の調査結果を見ると日本人は「仕事と生活のバランス」「社会とのつながり」の数値が世界的に見ても下位になっています。これは長時間労働をしている人の割合がOECD加盟国の平均より多いことによると考えられます。知人や地域の人との交流を通じ、良好な人間関係を築くことが健康と幸福感に大きな影響を与えることが多くの研究によって示されていますが、仕事中心の生活では社会とのつながりは希薄になりがちです。近年の「働き方改革」やコロナ禍を機にリモートワークなど柔軟な働き方が定着してきたため、「生活と仕事のバランス」は改善の傾向にはあるとはいえ、今後も政府・民間企業が力を合わせて取り組むことが必要です。人口減少社会において、希少な労働力を活かすためには、雇用や人事の面で「Well-being」の視点はますます重要となるでしょう。
最初に述べたとおり、私が就職した頃は、日本はバブル経済の最中にあり、私たちの世代は高級車やブランドの服など、ひたすら物質的な豊かさを追い求めていました。正直に申し上げますと、今でも自分の中にその名残である「物欲」が残っていることをしばしば感じています。
ところが、今の若者世代は必ずしも物の値段にこだわることなく、自分流に生活をエンジョイしているように見えます。多様な情報が簡単に入手できるネット社会になったことも、物質的な豊かさだけではない価値観やネットを通じた他人との関係性を重視する新しいライフスタイルを生み出している一因でしょう。就職活動に際しても、現代の大学生は、私たちの時代のように必ずしも大企業志向や出世欲ではなく、ワークライフバランスを重視し、自分の専門性や「やりたいこと」を第一に考えて志望企業を選ぶ傾向が見られます。身近な学生たちを見ていても、大学生の頃の自分よりずっと「Well-being」の本質を理解しているのではないかと思え、こうした若い世代に広がる価値観の転換が、やがて企業や政府を動かす原動力になるのではないかと感じています。
経済学は人々の満足度・幸福度を高める強力なツール

私たちが現在暮らしている⽇本社会は、急激な少⼦⾼齢化をはじめ多くの課題を抱えつつも⼀定の経済的な豊かさを実現しています。国際的に⾒てもわが国は失業者が極めて少なく、治安の⾯でも安⼼して暮らせる社会といえるでしょう。しかし⼀⽅で、⼈々の暮らしが、「会社」や「仕事」を中⼼に回っている⾯が今も残っており、それによって個⼈が地域社会や他⼈とのつながりを持つ時間が限られてしまったり、育児など家庭⽣活と仕事を両⽴させることが難しくなっている現実もあります。仕事が忙しいあまり趣味に打ち込む時間がなかなか持てず、個⼈の⼈⽣としては不⾃由な思いをすることも多いでしょう。しかし若い世代が「Well-being」の考え⽅を学ぶことで、⾃分⾃⾝の満⾜度だけでなく、仕事を通じて同僚や社会全体の満⾜度・幸福度アップにも貢献できる社会環境が⽣まれてくるはずだと私は信じています。現在、私は経済学部で「⽇本経済論」「経済政策論」「経済統計論」などの授業を担当していますが、「Well-being」に限らず、経済学は⼈々の満⾜度・幸福度を⾼めるためのさまざまな⼿段を考える際の強⼒なツールになる学問です。私の授業を聞いた皆さんが経済学の知⾒を⽣かして⾃分の⼈⽣を豊かにし、私たちが⽣きるこの社会の幸福度を⾼める⼈になることを⼼から願っています。