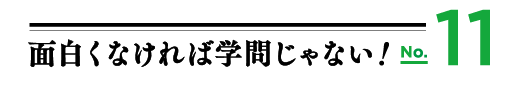
100年以上解読できない
「ヴォイニッチ写本」は
″ねつ造文書″なのか?
「ヴォイニッチ写本」は
″ねつ造文書″なのか?


#亜大の研究
安形 輝 教授
経営学部 データサイエンス学科
2024.11.01
シリーズ企画「面白くなければ学問じゃない!」では、亜細亜大学の教員陣の研究内容やエピソードを紹介します。第11回の特集は、経営学部 データサイエンス学科 安形 輝教授です。
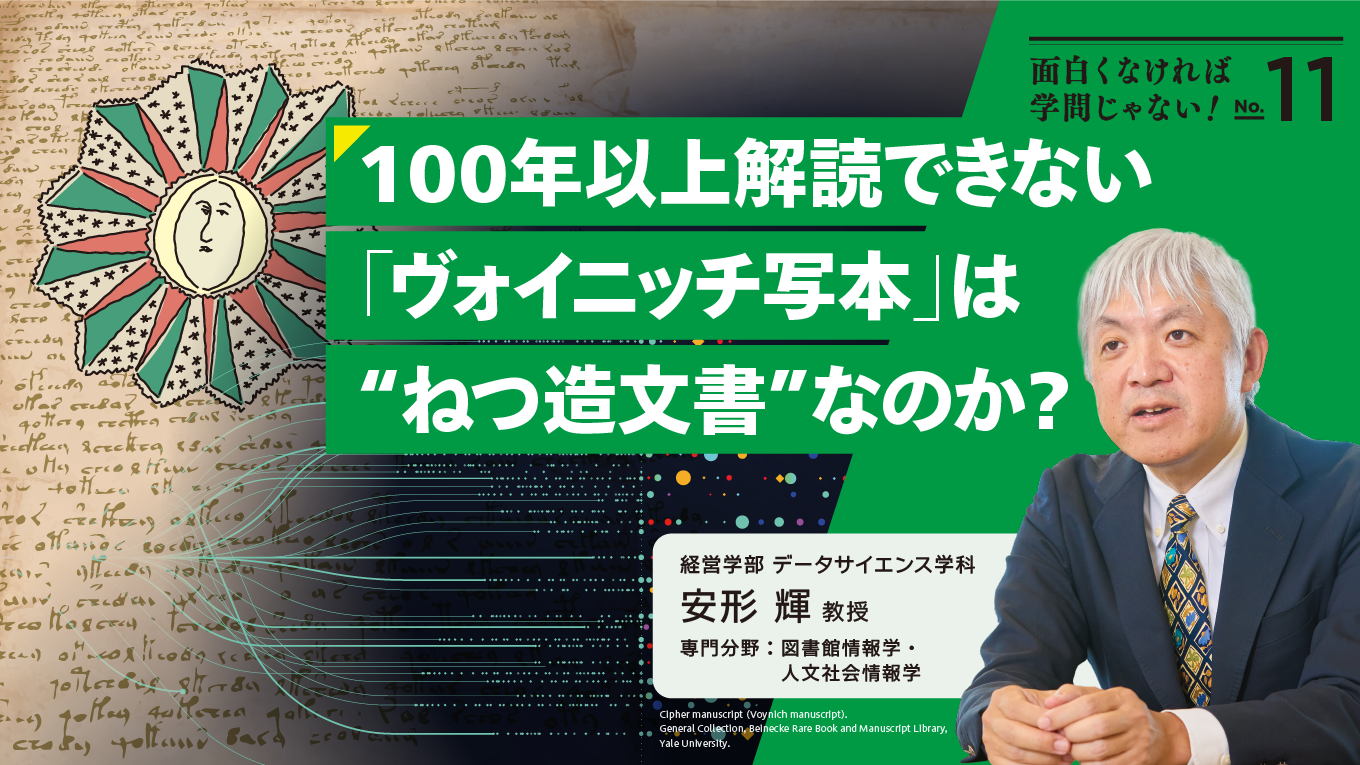
子どもの頃から、いつも身近に「本」があった
小学校時代は同世代の多くの本好きが夢中になった江戸川乱歩「少年探偵団」シリーズや子ども向けにリライト翻訳された「怪盗ルパン」シリーズを学校図書館で借りて読みました。中学生の時には大長編作品にチャレンジしようと栗本薫「グイン・サーガ」シリーズを夢中で呼んだことを覚えています。電車通学をするようになった高校時代は、通学時間を利用してハヤカワ文庫SFシリーズを一日一冊読むことを自分に課していました。
このように本好きの少年であった私は高校の系列大学に進学する際に当然のごとく「文学部」を選びました。文学部の中でも心理学と図書情報学の分野に興味を覚えましたが、悩んだ結果、最終的には「図書館情報学」を専攻。その頃の私の夢は「古本屋さん」でした。たくさんの古書に囲まれてのんびりとレジに腰掛け、時折、長時間の立ち読み客をハタキで追い払う(笑)。「たくさんの本に囲まれ」ているという点では、現在、大学教員、図書館長としてその夢の一部をかなえていると思います。
しかし、大学卒業を目前にするともっと「現実」を踏まえた進路を考える必要に迫られ、書籍に関わる仕事ということで大手印刷会社の就職試験を受けて内定をいただきました。ところが同時に大学の先生に大学院への進学を勧められ、私の心はそちらに引きつけられてしまったのです。
大学院では主に人がどのように情報を探すのかという「情報学」や「データベース」の研究に取り組んでいました。学部時代に図書館司書の資格を取得していたので、司書として大学図書館への就職も考えていたのですが、なかなか思い通りにはいかず、結局博士課程まで進学することになりました。私の経歴を見ると学部から大学院、現在の本学教員に至る道のりはスムーズに思えますが、実はその過程において自分自身ではつねに迷いがあり、時には流され、挫折し、いろいろあった上での現在があると思っています。でも今になって振り返るとそれこそが人生の面白さではないかとも思います。ちなみに「古本屋さん」の夢はまだ捨ててはいません。
「ヴォイニッチ写本」に書かれているのは「言語」なのか?
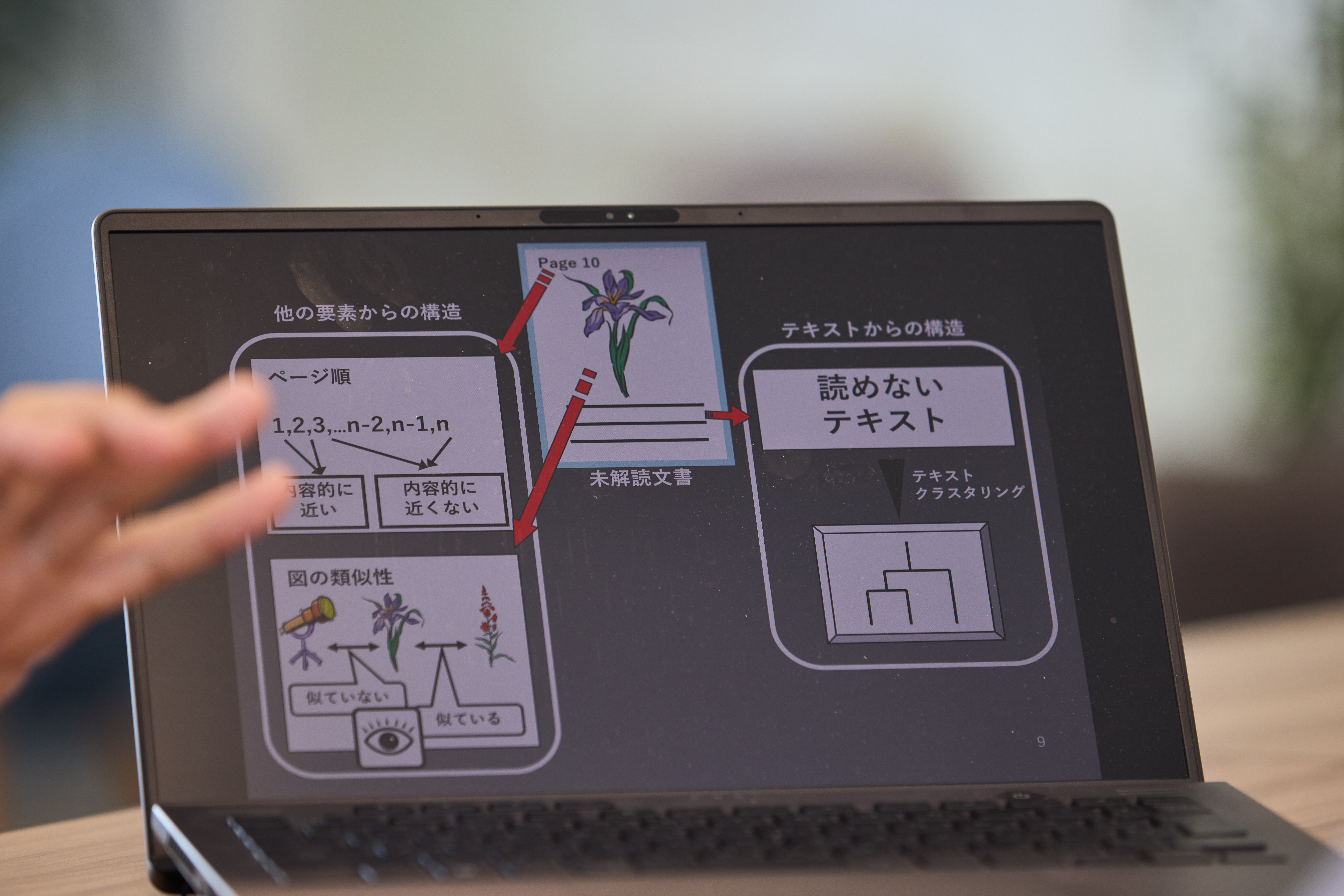
前述の通り、研究者としての私は図書館情報学などの広い意味での情報学、データベースなどを研究していました。研究に使うデータ分析手法の一つとして「テキストクラスタリング」というものがあります。これは複数のテキストを自動でさまざまなグループに分類するという手法です。
大学に就職してしばらくして私は、「ヴォイニッチ写本」と偶然ネットで出会いました。
「ヴォイニッチ写本」は何語で書かれているのかさえわからない「未解読文書」の代表的な存在で、いままで図書館情報学だけに限らず小説や音楽など、さまざまなところで話題となってきました。この写本は1912年にイタリアのある修道院で古書蒐集家であるポーランド系アメリカ人のウィルフリッド・ヴォイニッチが発見しました。発見以来、多くの歴史学者や言語学者、暗号の専門家などが解読にチャレンジしてきましたが、100年以上経った現在も何が書かれているのかはわかっていません。
現存するページが200ページ以上の「ヴォイニッチ写本」は、解読不能な文字と共に多くのページに植物、薬草壺、小さな裸の女性などの挿絵が描かれています。「ヴォイニッチ写本」に使われている羊皮紙を科学的に分析したところ15〜16世紀に製造されたと考えられており、また17世紀にはこの写本に言及したと思われる記録があります。
この古文書が何らかの意図で作成された意味をなさない「ねつ造文書」であるという説もありました。しかしながら書籍が富裕層の贅沢品であった中世ヨーロッパで、ねつ造文書のために200ページを超えるこれほど凝った手書きの写本が作成されたとはちょっと考えにくい……そのことがこの古文書が「ホンモノ」であるという信憑性を高めていました。そこで私は文書内容の「解読」ではなく、書かれている文書構造の有無、つまり「言語」が存在するのかという側面から解読可能性そのものを判定しようと考えました。
この研究は、たとえ現時点で解読不能な言語であっても、多くの言語に応用されている自然言語処理の手法が応用できるだろうという仮説に基づいています。たとえば「もし解読不能な宇宙人の言語で書かれたウェブページがたくさんあったとすると、それらのウェブページをGoogleでインデックス化すれば、宇宙人が使う言語のキーワードで検索できるはず」、そんなイメージの研究です。
近くにたまたま古い写本や印刷本の専門家がいたので、二人での共同研究となりました。そして2009年に発表した研究論文で、「ヴォイニッチ写本」の読めない本文と挿図・ページから推測される構造に関連性を見出すことで、決してデタラメな「ねつ造文書」ではない可能性が高いと判定することができました。それまで同様の分析をした研究者はいませんでしたから、この結果は新たな知見と言って良いと思います。
大学に就職してしばらくして私は、「ヴォイニッチ写本」と偶然ネットで出会いました。
「ヴォイニッチ写本」は何語で書かれているのかさえわからない「未解読文書」の代表的な存在で、いままで図書館情報学だけに限らず小説や音楽など、さまざまなところで話題となってきました。この写本は1912年にイタリアのある修道院で古書蒐集家であるポーランド系アメリカ人のウィルフリッド・ヴォイニッチが発見しました。発見以来、多くの歴史学者や言語学者、暗号の専門家などが解読にチャレンジしてきましたが、100年以上経った現在も何が書かれているのかはわかっていません。
現存するページが200ページ以上の「ヴォイニッチ写本」は、解読不能な文字と共に多くのページに植物、薬草壺、小さな裸の女性などの挿絵が描かれています。「ヴォイニッチ写本」に使われている羊皮紙を科学的に分析したところ15〜16世紀に製造されたと考えられており、また17世紀にはこの写本に言及したと思われる記録があります。
この古文書が何らかの意図で作成された意味をなさない「ねつ造文書」であるという説もありました。しかしながら書籍が富裕層の贅沢品であった中世ヨーロッパで、ねつ造文書のために200ページを超えるこれほど凝った手書きの写本が作成されたとはちょっと考えにくい……そのことがこの古文書が「ホンモノ」であるという信憑性を高めていました。そこで私は文書内容の「解読」ではなく、書かれている文書構造の有無、つまり「言語」が存在するのかという側面から解読可能性そのものを判定しようと考えました。
この研究は、たとえ現時点で解読不能な言語であっても、多くの言語に応用されている自然言語処理の手法が応用できるだろうという仮説に基づいています。たとえば「もし解読不能な宇宙人の言語で書かれたウェブページがたくさんあったとすると、それらのウェブページをGoogleでインデックス化すれば、宇宙人が使う言語のキーワードで検索できるはず」、そんなイメージの研究です。
近くにたまたま古い写本や印刷本の専門家がいたので、二人での共同研究となりました。そして2009年に発表した研究論文で、「ヴォイニッチ写本」の読めない本文と挿図・ページから推測される構造に関連性を見出すことで、決してデタラメな「ねつ造文書」ではない可能性が高いと判定することができました。それまで同様の分析をした研究者はいませんでしたから、この結果は新たな知見と言って良いと思います。
「図書館情報学」から見えてきた幅広い研究領域
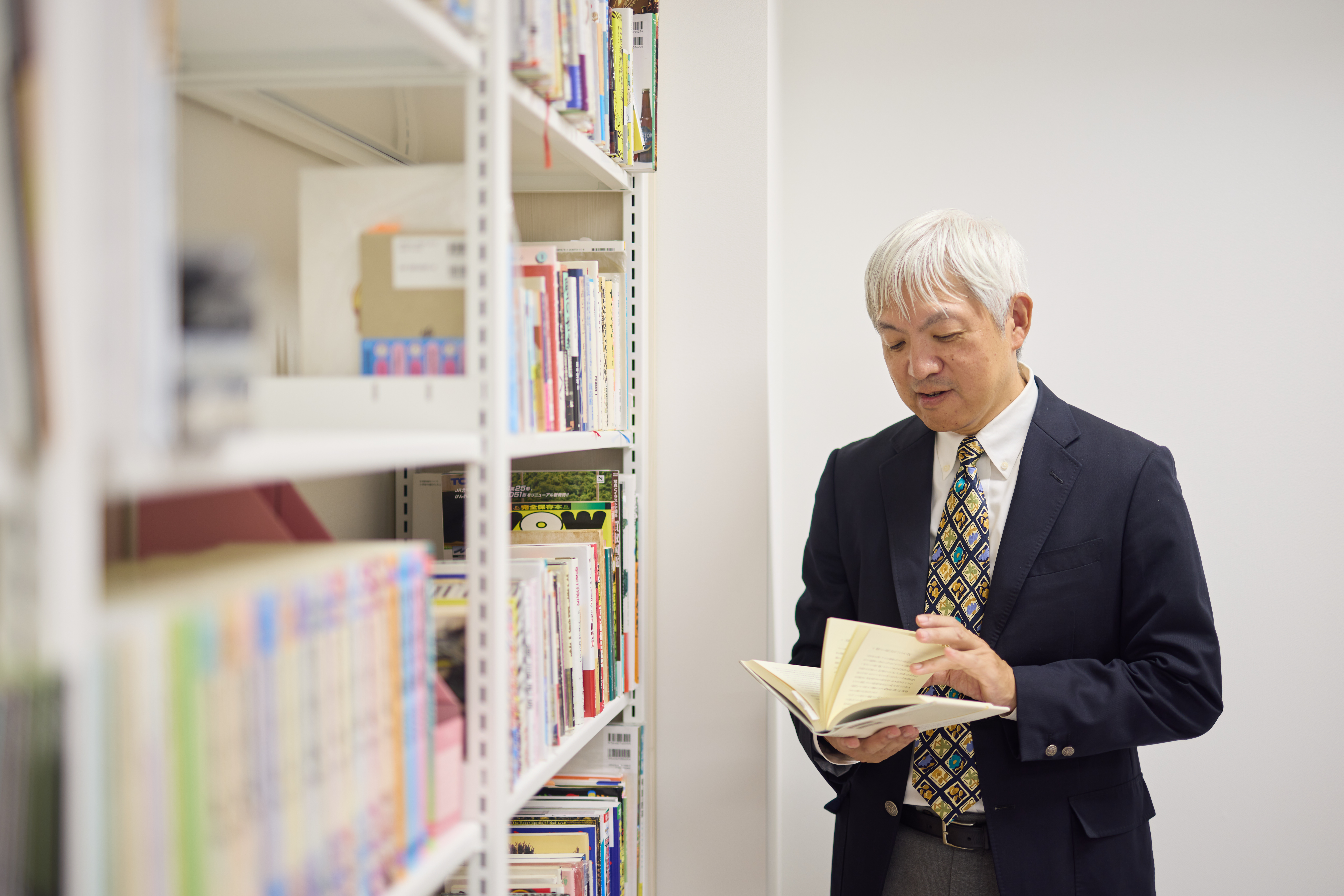
「ヴォイニッチ写本」の論文は言語学者や書誌学者だけでなく、幅広い人々から大きな反響を得て、研究者としての私にとって一つの転換点ともなりました。最初はネットで見つけた「未解読文書」への興味から始めた研究でしたが、その研究プロセスの中で〝図書館情報学〟のキーワードで手がけることができる研究テーマは非常に広範な分野に及ぶということを再認識させてくれたからです。
「ヴォイニッチ写本」に関しては今もさまざまな人々による、さまざまな角度からの「発見」が報告されており、私も引き続き関心を持ってその動向を追っています。
さらに現在は「マンガの国際化」、「絶版回収本」、「電子書籍」などの研究テーマも手がけるようになりました。このうち「絶版回収本」というのは、さまざまな理由で出版が打ち切られ、書店に流通したものまでが回収されてしまった本のことを言います。絶版となった理由は「内容の誤り」「名誉毀損」「差別用語等の使用」「プライバシー侵害」「著者の意向」など多種多様。実は私が中学生の時に愛読した前述の栗本薫「グイン・サーガ」シリーズの第1巻も、最初の版はある病気に関する表現で絶版・回収となり、作者が謝罪・訂正の上で改訂版が出されています。私は古書店やネット書店でこれらの絶版回収本を収集し、自分の研究室の書棚に「絶版回収本」のコーナーを設けています。ご興味がある方はぜひ研究室に来てください。一冊一冊、絶版になった理由や社会に与えた影響などについて詳しく説明させていただきます。絶版回収本を通してそれぞれの時代の人間や社会のあり方が見えてきてとても面白いですよ。
「ヴォイニッチ写本」に関しては今もさまざまな人々による、さまざまな角度からの「発見」が報告されており、私も引き続き関心を持ってその動向を追っています。
さらに現在は「マンガの国際化」、「絶版回収本」、「電子書籍」などの研究テーマも手がけるようになりました。このうち「絶版回収本」というのは、さまざまな理由で出版が打ち切られ、書店に流通したものまでが回収されてしまった本のことを言います。絶版となった理由は「内容の誤り」「名誉毀損」「差別用語等の使用」「プライバシー侵害」「著者の意向」など多種多様。実は私が中学生の時に愛読した前述の栗本薫「グイン・サーガ」シリーズの第1巻も、最初の版はある病気に関する表現で絶版・回収となり、作者が謝罪・訂正の上で改訂版が出されています。私は古書店やネット書店でこれらの絶版回収本を収集し、自分の研究室の書棚に「絶版回収本」のコーナーを設けています。ご興味がある方はぜひ研究室に来てください。一冊一冊、絶版になった理由や社会に与えた影響などについて詳しく説明させていただきます。絶版回収本を通してそれぞれの時代の人間や社会のあり方が見えてきてとても面白いですよ。
「面白そう」に「自分ごと」として取り組んでほしい

私のゼミは「図書館情報学」「メディア情報学」「データベース」などのテーマを掲げていますが、極力一人ひとりの学生の「面白そう」を優先して研究に取り組んでもらいます。大学生になったら親や学校の先生に言われたからではなく、自分の興味・関心を大切にしてほしいからです。私自身がそうであったように大学時代に必ずしも明確な関心や目標が見つかるわけではありません。しかしつねに心の中で「面白そう」と思えることを探し続けて、それが見つかったら「自分ごと」として取り組むことに「大学で学ぶ」意味があると思っています。社会人になる手前の大学生という時期は迷いや失敗を恐れずにチャレンジすることができる貴重な時期でもあります。ぜひ有意義に使ってください。
また私たち大学側も、時代と共に変化し、多様化する学生のニーズにしっかり対応する教育を用意する必要があるでしょう。多くの貴重書・古い写本などを所蔵する大学図書館も、社会インフラとしてネットやデジタルが一般化する現在、どのようなサービスを提供していくかが問われています。私も図書館長として、電子書籍の研究者として、大学生のみなさんのご意見をうかがいつつ、新しい図書館のあり方を考えていきたいと思っています。
また私たち大学側も、時代と共に変化し、多様化する学生のニーズにしっかり対応する教育を用意する必要があるでしょう。多くの貴重書・古い写本などを所蔵する大学図書館も、社会インフラとしてネットやデジタルが一般化する現在、どのようなサービスを提供していくかが問われています。私も図書館長として、電子書籍の研究者として、大学生のみなさんのご意見をうかがいつつ、新しい図書館のあり方を考えていきたいと思っています。