
データサイエンスで
音楽の進化を分析し
音楽の未来を予測する
音楽の進化を分析し
音楽の未来を予測する


#亜大の研究
堀 玄 教授
経営学部 データサイエンス学科
2025.08.01
シリーズ企画「面白くなければ学問じゃない!」では、亜細亜大学の教員陣の研究内容やエピソードを紹介します。第15回の特集は、経営学部 データサイエンス学科 堀 玄教授です。
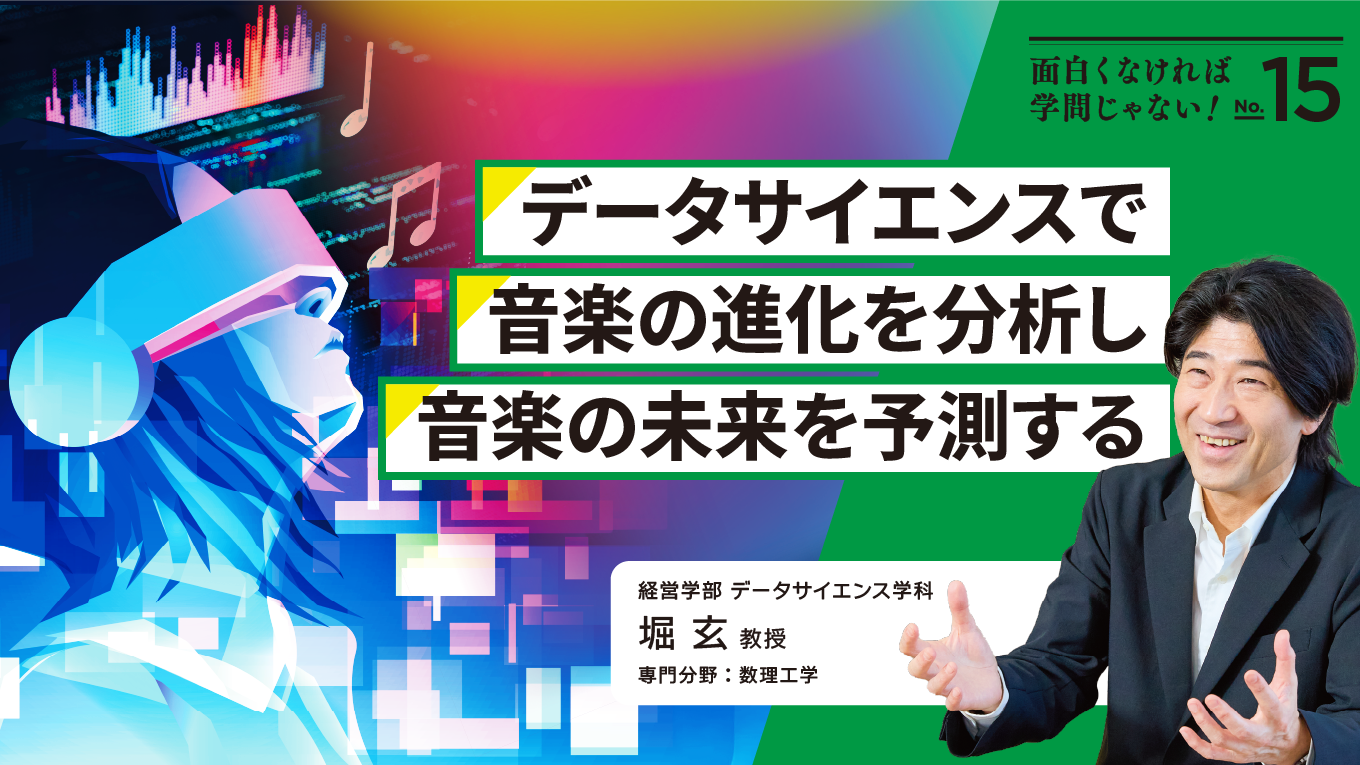
現在のAIの基礎を築いた研究先駆者のもとで学ぶ
趣味だった「音楽」が、やがて自動作詞システムの開発に結びつく

数理工学、脳科学の研究者だった私が、なぜ「音楽」を研究対象としたのか?まず数理工学やデータサイエンスは、世の中のあらゆるモノを分析対象とする研究分野ということがあります。当然「音楽」もその対象に入ってくるわけです。もう一つ、私自身が10代の頃からバンド活動やコンピュータ音楽に熱中した音楽マニアだったこともあります。小学校高学年ぐらいでシンセサイザーとコンピュータを駆使したYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)の音楽に衝撃を受け、中学生からはバンド活動を開始。大学時代にはバンドだけではなく、YMOの坂本龍一さんに憧れてコンピュータ音楽の制作にも取り組みました。さらに大学院生になると趣味が高じてレコード会社でアレンジャーの仕事を引き受けるようになりました。当時は大学研究室とレコード会社のスタジオを行き来する生活で、寝る時間も取れないほどの忙しさだったことを思い出します。それでも当時は「研究」と「音楽」は別物でした。その2つが結びついたのは、亜細亜大学の教員となって数年後、とある学会で自動作曲システム 「Orpheus(オルフェウス)」の開発者である嵯峨山茂樹先生(東京大学名誉教授)と知り合ったときでした。嵯峨山先生は「Orpheus」に自動作曲機能だけではなく、自動作詞機能も持たせたいと考えられており、その研究を私に依頼したのです。自動作詞を実現させるために必要なのは、いわゆる「自然言語処理(NLP)」というコンピュータが人間の言語を理解してコミュニケーションできるようにする技術です。亜細亜大学で学生たちにも教えていたこの技術を使えば自動作詞システムはできるはず……。その後なんとか世に出すことができたJ-POPの自動作詞システムは大いに話題となり、2015年の紅白歌合戦直前、私は嵯峨山先生とともにNHKの特別番組に出演することになりました。番組からは「2020年代に流行る曲のトレンドワード」を予測するという課題も与えられ、当時最先端だったword2vecという手法を使って導き出したのが「僕ら」「場所」「すべて」の3つのワードでした。実は私自身その予測のことをしばらく忘れていました。最近、番組の動画を見た学生から「先生の予測は当たっていたのですか?」と問われたので、あらためて調べてみると、「僕ら」と「すべて」はKing
Gnuや米津玄師などが使用するワードの上位にあり、ちょっとホッとしています(笑)。
データサイエンスで人が生み出す音楽の進化と未来を分析する

「Orpheus」の自動作詞システムを開発してから10年の間、AIは飛躍的な進歩を遂げました。2022年には博報堂のプロジェクトで、私がこのために新たに開発した自動作詞システムを活用して、各年代のヒット曲に高い頻度で登場するワードなどを反映した「ヒンド(頻度)ソング」のAIによる作詞にも関わりました。しかし今やChatGPTなどの生成AIを使えば誰もが同じようなことをできるようになりました。そのため現在は亜細亜大学の同僚である東条先生とともに、音楽の進化とその未来についてデータサイエンスを駆使して予測するという壮大な研究に取り組んでいます。この数百年の間、古典音楽からジャズ、ポピュラー音楽、ロック、電子音楽、ラップ・ヒップホップなど、歴史の中で音楽は複雑に枝分かれしながら進化、多様化してきました。その複雑なプロセスを数理工学、データサイエンスを駆使して分析。この先の未来にどのような音楽が流行するのか、音楽の創り手だけではなくリスナーやファンといった受け手の変化にも注目して「音楽の未来」を描くことができればと思っています。東条先生によると、特権階級を対象にしたクラシック音楽から大衆音楽であるジャズやポピュラー音楽への分岐点は、「月の光」で知られるフランスの作曲家クロード・ドビュッシーなのだそうです。今後、マイルス・デイヴィスやチャック・ベリー、ビートルズなども大きな分岐点と位置づけられるかもしれません。この研究は独創的・先駆的な研究を助成する科学研究費助成事業(科研費)に採択されました。その研究成果が、わが国が海外に発信するソフトパワー増強のために少しでも役立つことができればこれほどうれしいことはありません。
データサイエンスを使ってあなたがやりたいことは何ですか?

私はデータサイエンス学科で、AIの開発にも使われる「Python(パイソン)」というプログラミング言語を使ってデータサイエンスの基礎を教えているほか、音楽制作ソフトや動画制作ソフトを使って実際に「つくる」楽しさを味わえる授業を多く担当しています。数理工学やデータサイエンスでは、言語や音楽だけでなく、医療、スポーツ、アートなど世の中のあらゆるモノが分析対象となります。データサイエンスやAIはあくまでもツールであり、それを使って「何をつくりたいか」「何を分析したいか」「何を予測したいか」といったことが研究のモチベーションとなります。私の研究室では学生の好奇心や関心を優先して、それぞれやりがいを感じられる研究テーマに取り組んでもらっています。とはいえ研究室配属1年目の3年生ではまだその「何を」の部分がはっきりしない学生が多いことも事実です。そんな学生に対しては私もサポートしながら、研究室の仲間とともに1年間かけて研究テーマを見つけてもらうようにしています。数理工学、データサイエンスの手法を使い、研究目的が明確であれば、私のゼミではかなりユニークな研究もできると思います。中にはデータサイエンス分野での起業をめざす学生もいて、データサイエンス学科の前身となるデータサイエンス副専攻の卒業生では、実際に会社を立ち上げて、今では世界を飛び回って活躍している人もいます。データサイエンスを使ってやりたいこと、分析したいことがある人は誰でも歓迎します。もちろん音楽が好きな人は大歓迎。現在の若い世代が好む音楽やトレンドについては、私がぜひ皆さんから教えてもらいたいと思っています。