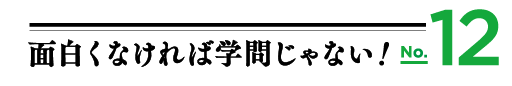
如果你学习印度,
生活的“兴奋”
一定能看到。
生活的“兴奋”
一定能看到。


#亚大的研究
小矶千寻教授
国际关系学院多文化交流系
2024.12.01
系列项目 "如果不有趣,那就不是学术!"介绍了亚细亚大学教师的研究成果和作品。国际关系学院多文化交流系小矶千寻教授

从我记事起,我就喜欢“印度”
这样喜欢印度的一面随着成长不断膨胀,终于在大学时代和两位女性朋友一起踏上了第一次向往的印度之旅。
目的地是印度西海岸,面向阿拉伯海的大都市孟买 (旧孟买) 。当我降落并站在飞机的舷梯上时,我被热情的热情所包围,我强烈地想到“我想住在这里!”。尽管还没有踏上印度大地。有些人可能会觉得印度的空气“臭”,但对我来说,这是一种非常放松的美妙气味。
长达1个多月的第一次印度之旅,无论去哪里都很开心,留下了深刻的回忆。当我继续旅行时,“我想有一天住在印度”的感觉变得越来越强烈,我的朋友们安抚我,他们发出了“想去这个国家留学!怎样才能住在印度?”的声音 (笑) 。然而,当时我根本没有想到我会成为印度思想和文化的研究者。和学院派无关,只是喜欢印度,想住在这个国家。
如果你追求“我想知道”“我想生活”,那就去研究人员的方式

为了在印度生活,学习印度的官方语言——印地语是必不可少的。大学毕业后,我在日本只学习了印地语的基础知识,之后就去了印度,在语言学校开始学习印地语。然而,这并不是一次以学习为核心的留学经历,而是在享受印度生活和旅行的同时,学习了语言和文化。
印地语使用天城体文字,看起来像是一种编码字母。乍一看,它似乎是一种非常难学的语言,但实际上它的语序与日语相同,元音的发音也比英语简单,所以对日本人来说,它可能是一种更容易学习的语言。我目前在亚细亚大学教授印地语。在日本,很少有大学可以学习这门语言,所以我鼓励对印度感兴趣的学生接受挑战。
那时,我住在马哈拉施特拉邦一个叫瓦尔达的小镇,那里位于广袤的印度中部。瓦尔达本身是个乡村小镇,但坐火车去哪儿都很方便,所以我背包游历了印度各地。印度幅员辽阔,足以容纳整个欧洲,因此从东到西、从北到南,这里汇聚了不同的文化、语言和种族,无论你走多远都不会感到厌倦。印度南部的人们谦逊、悠闲、舒适,但我最喜欢印度的东北部地区——恒河流域。这里的人们直率地表达自己的感情,有些人甚至会在见到年轻女孩时就说“我们结婚吧!”(笑)。但我更欣赏充满活力和真诚的印度人民。
印地语使用天城体文字,看起来像是一种编码字母。乍一看,它似乎是一种非常难学的语言,但实际上它的语序与日语相同,元音的发音也比英语简单,所以对日本人来说,它可能是一种更容易学习的语言。我目前在亚细亚大学教授印地语。在日本,很少有大学可以学习这门语言,所以我鼓励对印度感兴趣的学生接受挑战。
那时,我住在马哈拉施特拉邦一个叫瓦尔达的小镇,那里位于广袤的印度中部。瓦尔达本身是个乡村小镇,但坐火车去哪儿都很方便,所以我背包游历了印度各地。印度幅员辽阔,足以容纳整个欧洲,因此从东到西、从北到南,这里汇聚了不同的文化、语言和种族,无论你走多远都不会感到厌倦。印度南部的人们谦逊、悠闲、舒适,但我最喜欢印度的东北部地区——恒河流域。这里的人们直率地表达自己的感情,有些人甚至会在见到年轻女孩时就说“我们结婚吧!”(笑)。但我更欣赏充满活力和真诚的印度人民。
"朱加尔"是印度人全球活跃的原动力?

即使在印度生活了四年,我对印度的了解之心依然不减。于是我决定去浦研究生院攻读研究生院哲学专业。浦那大学所在地马哈拉施特拉邦的浦那是一座堪比英国剑桥、牛津的学术之城,国家级研究机构和大学云集于此。浦那地处高原,气候比日本的夏天更加舒适。在攻读硕士期间,我遇到了从日本留学的丈夫。回国结婚后,我们一起回到浦那大学攻读博士学位,并决定走上研究者的道路。
我主要研究印度最大的宗教——印度教的哲学。我仍然每年访问印度一次,对我最初居住的马哈拉施特拉邦人民的生活和文化进行田野调查,尤其是他们的饮食文化和宗教。我还出版了一本面向公众的关于印度饮食文化的书籍。近年来,我还专注于宗教仪式中使用的香(或香料)的田野调查。
顺便提一句,印度如今在国际社会中正展现出其独特的存在感。例如,在美国,包括硅谷在内的许多公司中,印度裔管理人员的数量正在增加,英国前首相也拥有印度血统。此外,在日本,领先的煎饼和煎饼制造商龟田制果株式会社的现任首席执行官也是一位曾在大阪大学和名古屋大学担任研究员的印度人。如此看来,印度人在海外取得了令人瞩目的成就,我认为其中一个原因就是印度人经常使用的“jugaar”(注:此处原文有误,无法准确翻译)这一概念。
“Jugirl”的意思是“快速解决方案”。这个词用来描述当你面临一个难题,而你没有时间或手段去解决它时,你会利用手头上现有的任何材料,甚至稍微改变一下规则来解决问题。
即使在大多数人都会放弃的情况下,许多印度人仍然拥有一种“Jugaal”(不屈不挠)的精神,这种精神促使他们“竭尽所能,克服一切”。印度教是一个多神教,吸纳了来自各个地区的神祇,其宽容精神也可以说是基于这种“Jugaal”。据说,现在美国大学的“管理哲学”讲座也开始讨论这个问题。
我主要研究印度最大的宗教——印度教的哲学。我仍然每年访问印度一次,对我最初居住的马哈拉施特拉邦人民的生活和文化进行田野调查,尤其是他们的饮食文化和宗教。我还出版了一本面向公众的关于印度饮食文化的书籍。近年来,我还专注于宗教仪式中使用的香(或香料)的田野调查。
顺便提一句,印度如今在国际社会中正展现出其独特的存在感。例如,在美国,包括硅谷在内的许多公司中,印度裔管理人员的数量正在增加,英国前首相也拥有印度血统。此外,在日本,领先的煎饼和煎饼制造商龟田制果株式会社的现任首席执行官也是一位曾在大阪大学和名古屋大学担任研究员的印度人。如此看来,印度人在海外取得了令人瞩目的成就,我认为其中一个原因就是印度人经常使用的“jugaar”(注:此处原文有误,无法准确翻译)这一概念。
“Jugirl”的意思是“快速解决方案”。这个词用来描述当你面临一个难题,而你没有时间或手段去解决它时,你会利用手头上现有的任何材料,甚至稍微改变一下规则来解决问题。
即使在大多数人都会放弃的情况下,许多印度人仍然拥有一种“Jugaal”(不屈不挠)的精神,这种精神促使他们“竭尽所能,克服一切”。印度教是一个多神教,吸纳了来自各个地区的神祇,其宽容精神也可以说是基于这种“Jugaal”。据说,现在美国大学的“管理哲学”讲座也开始讨论这个问题。
生活的能量需要兴奋

我在印度的生活经历,让我体会到以“不费脑筋的精神”迎接挑战的重要性,这种精神在《Jugal》中也有体现。即使失败了,印度人也会一笑置之,说“没问题”,然后继续迎接下一个挑战。在日本人看来,这或许显得厚颜无耻、漫不经心。然而,从印度人的角度来看,日本年轻人不愿接受挑战,失败一两次就精神失常,这似乎有些奇怪。
我也希望我教的年轻人拥有“Jugirls”和“努力拼搏的精神”,以及生活所需的能量。要做到这一点,至关重要的是要对一切事物保持好奇心,并找到真正让你兴奋的事物。我从小就对“印度”充满热情,从未感到厌倦。我希望通过我的课程和研讨会活动,至少向我的学生们传达一点印度的乐趣和无穷魅力。
首先,对印度美食和电影感兴趣就足够了。我有很多关于“Jugaar”的有趣故事,这些故事都是我在印度经历的,所以如果你感兴趣的话,欢迎来参观我的教研馆。我还可以向你介绍大都市地区美味的印度餐厅,还可以教女学生如何穿着印度传统服饰——纱丽。
我相信,通过接触与日本人不同的印度生活方式和文化,年轻一代一定会改变他们对周围社会和自身的看法。让我们一起透过印度不同文化的滤镜,寻找真正让你兴奋的东西吧!
我也希望我教的年轻人拥有“Jugirls”和“努力拼搏的精神”,以及生活所需的能量。要做到这一点,至关重要的是要对一切事物保持好奇心,并找到真正让你兴奋的事物。我从小就对“印度”充满热情,从未感到厌倦。我希望通过我的课程和研讨会活动,至少向我的学生们传达一点印度的乐趣和无穷魅力。
首先,对印度美食和电影感兴趣就足够了。我有很多关于“Jugaar”的有趣故事,这些故事都是我在印度经历的,所以如果你感兴趣的话,欢迎来参观我的教研馆。我还可以向你介绍大都市地区美味的印度餐厅,还可以教女学生如何穿着印度传统服饰——纱丽。
我相信,通过接触与日本人不同的印度生活方式和文化,年轻一代一定会改变他们对周围社会和自身的看法。让我们一起透过印度不同文化的滤镜,寻找真正让你兴奋的东西吧!