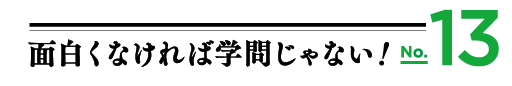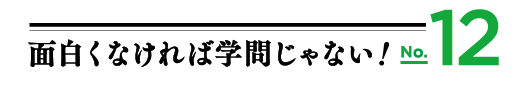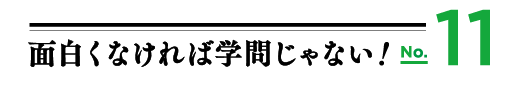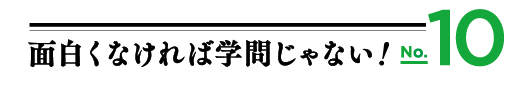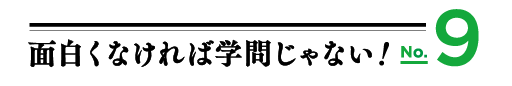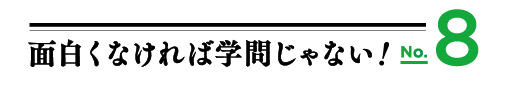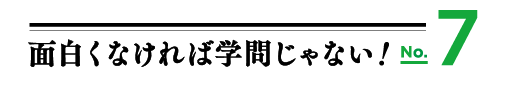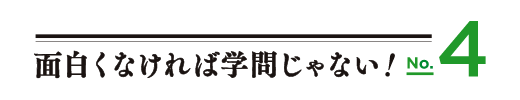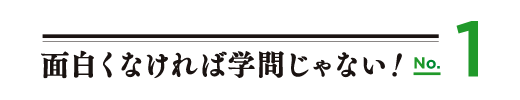見つけよう、自分だけの###################
#「人を幸せにする街づくり」が、わたしのミッション #2度の留学は、私に気づきと成長をもたらしてくれた #ピアサポーターや課外活動で、理想の「働く姿」が見えた #プログラミングもゲーム理論も、将来の夢への糧 #世界の広さを感じるキャンパスで、
実践力を身につける #デフサッカー日本代表として世界に挑み、大学生活との両立で充実した日々を送る #奇跡は自分で生む。自ら世界に進もう。 #亜細亜大学で培った好奇心と挑戦で可能性を広げていきたい
在学生や卒業生の今の気持ちや活躍、教員の研究、大学の取り組みをご紹介していきます。
#すべて
背景色を決めます。
all
#亜大を選んだ理由
背景色を決めます。
reason
#亜大の学び
背景色を決めます。
learning
#亜大の留学
背景色を決めます。
abroad
#亜大の学生生活
背景色を決めます。
life
#亜大のキャリア
背景色を決めます。
career
#亜大の研究
背景色を決めます。
study
- 在学生
- 留学生
- 卒業生
- 教員
- 経営学科
- ホスピタリティ・マネジメント学科
- データサイエンス学科
- 経済学科
- 法律学科
- 国際関係学科
- 多文化コミュニケーション学科
- 都市創造学科